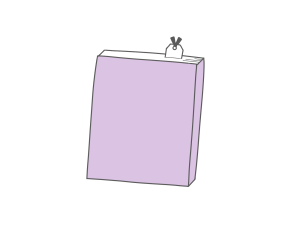③「わからない」という方法 橋本治を読んで|教えるのが上手≠頭がいい|教えるために大事なこと
こんにちは。
(前回の記事はこちらから→「②「わからない」という方法 橋本治を読んで|あなたは何様ですか?部長様?お客様?神様?」)
今回の③で『「わからない」という方法』については最後です。
編み物というのは、やっぱり「女のするもの」である。女がやって、女が教える。その女の多くはオバサンであり、私に言わせれば、オバサンの教え方には二つの欠点があるのである。
一つは「わかりやすさの押しつけ」であり、残る一つは「生真面目さの押しつけ」である。
オバサンは、自分がふだん当たり前にやっていることを、「いたって簡単なこと」と理解している。だから、「ほら、簡単でしょ、簡単でしょ」と言うばかりで、わからないでいる人間の頭の構造を理解しないで、「わかりやすさ」の押しつけをする。
と同時に、「ほら、もっとちゃんとやって!」と生真面目さを押しつけてしまう。
わからないでいる人間がわからないままにウロウロしている状態が、自分のやっていることを「神聖」だと思う人には、「神聖さを愚弄する侮辱行為」と見えてしまうのである。
「わからない」という方法 橋本治 p.82
「インストラクショナルデザイン」という本の感想記事も書こうと思っているのですが、「教える」ってすごく奥が深いことだと思います。
私は子どもの頃、比較的従順な子でした。
「勉強しなさい」と言われたときに「はぁ…しょうがない。やりたくないけど、やらなきゃいけないんだったらやるかぁ」みたいなタイプ。
でも「勉強しなきゃいけない」「勉強は大事だ」ということは理解していても、天才的な成績を取れたわけではありませんでした。
私の両親は教育の専門家ではなく、教えることも上手くなかったため、私の成績を上げようとしてかける言葉は「ちゃんとしなさい!」とか「真面目にやりなさい!」でした。
別に私は「ちゃんとしないようにしよう!」とか「なるべく不真面目にやるように頑張ろう!」って思っていたわけではないんですよね…。
だけど両親から見れば「不真面目に振る舞って、侮辱しようとしているんだな!」みたいに思えたのかもしれません。
子どもは頑張ろうとしているし、親も子どもに頑張ってほしい・成績を上げてほしいと思っているはずなのに、コミュニケーションがチグハグで平行線。
交わした言葉が全く意味を成していません。(苦笑)
「教える」とか「コミュニケーションをとる」「指示を出す」「行動を促す」といったことを、あまり簡単だと思って軽視しないほうが、自分・相手・周囲のためにもいいんじゃないかな~と私は思っています。
「教える」ために最も大事なこと
ところで、「教える」という単語の意味をgoo辞書で検索してみたところ、こう出ました。
- 知識・学問・技能などを相手に身につけさせるよう導く。
- 知っていることを相手に告げ知らせる。
- ものの道理や真実を相手に悟らせて導く。
(参考→「goo辞書」)
おそらく引用部分の”オバサン”がやっているのは2番なのでしょう。
「言ったよね、見せたよね、だからできるよね」という感じ。その後に「生徒ができるようになるまで導く」という態度と行動がありません…。
(でも2番の意味も「教える」に含まれるのだから、その”オバサン”先生を否定することはできませんね…。)
教えるのが上手な人≠頭がいい人
私は大学生のときに個人指導塾と家庭教師をやっていたことがあります。(それ以外もやっていました。)
そうした「教える」という仕事に携わったり、近くで見たことがない人は、「頭の良い人が先生になる」と思っていますが、実際は違います。
引用部分に”わからないでいる人間の頭の構造を理解しないで、「わかりやすさ」の押しつけをする”とありますよね。
この”わからないでいる人間の頭の構造を理解”できることのほうが、「教える」にあたって重要な要素なのです。
だって…「講師本人は超モテモテだけど、生徒を全く変化させてあげられない婚活塾」と「講師本人はそこそこしかモテないけれど、生徒が次から次へと幸せな交際や結婚を達成している婚活塾」だったら、後者のほうがいいですもんね。(笑)
私も塾講師のアルバイトをやってみて実感しました。
年度の初めに、生徒って学校配布のワークブックとその答えをもらっているんですよ。つまり、答えが何になるかはわかっているんです。
でも、その答えがどう出てきたのかが、わからない。途中式や解説も書いてあるんだけど、それが何を言わんとしているかがよくわからない。
そんな時、私たち塾講師が文字になっていることを図にしたり表にしたり、違う日本語で言い換えたり、なぜそれが必要なのかの理由を説明したり…と補足情報をプラスしてあげることで「わかった!」と納得してもらえるんです。
頭が良すぎる人は、何の(誰の)解説もなしに教科書などをパッと見ただけで完全に理解できてしまうので、「えっ?これ以上どうやって簡単にしろというの?」「どうしてわからないの?」と、”わからないでいる人間の頭の構造を理解”することができません。
だから最低限の学力さえあれば、「頭がいいかどうか」はさほど重要ではないのです。(重要じゃないことはないが、もっと重要なことがある。)
整理してみると
- 頭がいいし、教えるのも上手
- 頭はいいが、教えるのは下手
- 頭は悪いが、教えるのは上手
- 頭が悪いし、教えるのも下手
というパターンがありそうです。
頭がいいというのは、今回はペーパーテストでいい点を取れるということにしておきましょうか。そしてこの「頭がいい」の部分は「編み物が上手い」とか「足が速い」とかにも置き換えられますね。
みんながみんな1番であればいいのかもしれませんが、世の中そう思い通りにもいきません。
そうなったとき、「2番の人が優秀で頼りがいがありそうだから、あの人を教育係にしよう」「優秀なあの人から技を教えてもらえば、みんな上達するに違いない」「私は編み物が上手いから、編み物講師に向いているはず」と教える適性を考えずに決めるのは早すぎます。
「教える」は(免許が必要な仕事でない限り)「誰でも挑戦していいこと」ではあるけれど、「誰でも簡単に、何の工夫もなく上手にできること」ではありません。
おそらくそこに勘違いがあるからこそ、「今見せたからできるよね、簡単にすぐできるよね」「できないのは、ちゃんとやってないからだ」とわかりやすさ・生真面目さの押しつけが生まれてしまうのではないでしょうか。
教えるのが上手ってどういうこと?
こんなことを言っている私ですが、教えるということにいまいち自信が持てません。
数年前に「教える仕事が向いている」と占い師さんに言われてはじめて、「私は将来的に教える仕事をするんだろうか?」と頭の中にチラつくようになりました。
学校の同級生や、職場の後輩に教えたことはあるのですが、一般のお客様を相手にお金をもらって教える仕事をするとなると、気持ちが引き締まります。
(「お金もらって塾講師と家庭教師やってたんだよね?」と言いたいところですが、大学生の頃はまだ社会を知らなかったので、今よりも怖いもの知らずだったのです…。)
私は「仕事」っていうのは「やればいいや」じゃなくて、限られた時間や予算の中で、お客様に最もいいものを提供するためにあると思っています。
雑な気持ちで取り組みたくはありません。だって「そこそこ」でいいのなら、ボランティアとかブログとかYouTubeとか、無料や格安でできる手段でもかなえられることじゃないですか。
そんな無料でできることの域を超えて、もっといいものを作らなければならないから、お客様からお金をいただいて、仕事をするわけですよね。
だったら魂込めて真剣にやったほうがやりがいもあって楽しいはずです。
(「君は真面目すぎる」と言われたことは一度ではないが、そんな自分も嫌いになりきれない。(笑))
ということで、どうせ教える仕事をするなら真剣にやりたい私は「じゃあ、教えるのが上手いってどういうこと?」「っていうか、教えるってそもそもどういうこと?」と考え始めました。
「教える」についての本や、教えることが上手になるための講座、教材づくりの基本を学べるものはないかと探していました。
大きい本屋さんをウロウロして探したのですが、「教えるのが上手になる」というよりも「小学校の教員になる」「学校の授業をつくる」ことを目的とした本しか見つけられませんでした。
そんな中、やっと1冊見つけられたのが「インストラクショナルデザイン」だったのです。
というわけで、「インストラクショナルデザイン」の記事では「教えるのが上手いとは何なのか」「上手くなるためにはどうしたらいいのか」を考察していくことにします。
今回はここまで!
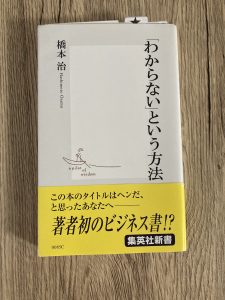
ここまで読んでくださり、ありがとうございます。(^_^)/~