「本を出したい人の教科書 – 吉田浩」1章を読んだ感想|楽しい=悪!?|売れない本=よくない本!?|私の仕事への思い
こんにちは。
この本を買ったのは2020年7月12日。
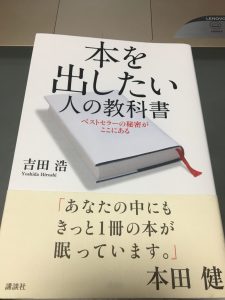
7月26日には「本を出したい人の教科書」を読んだ感想⓪」というタイトルでブログにアウトプットしていましたが、リライトすることにしました。
最近、ミニマリストさんのYouTubeを見ていて、やっぱり物を減らしたいなと思うんですよね。私は卒業アルバムとか服は、一切ためらいなく手放せたのですが、本が全然手放せません。
(関連記事→「ヒトはなぜミニマリストに憧れるのか|本が捨てられない人の心理|責任感が強い?|ゆるゆるミニマリストを目指す」)
人によって何を捨てづらいか(私は捨てるだけじゃなく売る・寄付でもOK派)は様々だと思いますが、「しっかり役立てられた」「ちゃんと活用した」「満喫できた」という実感がないと、「もったいない」という気持ちが湧いてくるのではないでしょうか?
この本を手放すか少量残す中に含めるのかはまだ決まっていませんが、読書ノートをつけたり、ブログなどで紹介することによって「十分に味わったんだから大丈夫!」と思える気がします。
「本の紹介って著作権の侵害にならないんですか?」という質問をよく見かけますし、私自身も以前そう思っていました。数字だけで単純に判断できるものではないけれど、目安として引用20%:オリジナル80%ぐらいで、あくまで自分が作りだしたものがメインであり、出所が明記されていれば大丈夫なようです。
(参考→「impress > 『クリエイターのための権利の本』(全6回) > 著作権と引用の5条件! 動画や歌詞を掲載する場合の注意点とは?」)
というわけで、私がビビッと来た文を拾いながら、私の考えや感想・体験などを盛り込んで書いていきたいと思います。
目次
出版に寄せて 本田健|出版は社会的事業
著者がどうしてその本を書こうと思ったのか、動機が大事だと言うのです。その動機が自分のためでなく多くの人のためであれば、その本は売れやすいと言います。
「本を出したい人の教科書」p.2
「出版は、社会的事業なので、少数の人にしか届かなくても出さなければいけない本がある」という言葉にしびれました。
「本を出したい人の教科書」p.2
1章の前に「出版に寄せて」がありますが、私はここを読んだ時点でこの本(著者)のファンになりました。ターゲットの心を掴むのを狙って書かれているんでしょうか。(笑)
その可能性は少なくなさそうですが、どうせ読むなら気持ちよく読みたいですから、こうやって読者をときめかせることを書いてくれるのは嬉しいですね。私も電子書籍を執筆するときに意識しておきたいところです。^-^
なぜ私がこの文でときめいたかというと…
実家に住んでいた頃は自分と両親の意見の違いに悩み、「こんな風に考えてしまう自分が悪いんじゃないか」と自己嫌悪になることがありました。そこに「あなたの考えでもいいんだよ、変じゃないよ」って光を照らしてくれたような感覚を得られたから、ときめいたんです。
両親は「つまらないことを嫌々、苦痛に耐えながら一生懸命やるのが仕事なんだ!好きなことを仕事にできるのなんて世の中のほんの一握りなんだから、凡人である私たちがそんなことを考えてはいけない!」といつも言っていました。
楽しい=悪!?|苦しい=善!?|昭和の根性論の名残り
以下の記事で厚切りジェイソンさんがコメントをされていますが、私もこのように思います。
ジェイソンさんは「なんで? 逆に仕事楽しまないと人生つまらないと思うけどな」「『楽しい=不真面目』と勘違いしている日本人多いな」と疑問を呈しました。
東洋経済 > 日本人が「世界一、仕事が苦痛」と感じる根本理由 -2 –
楽しいことが悪いことで、苦痛に耐えることが価値だって思い込んでいる人が多い気がします。
昭和の時代の学校の部活動では、「ジャンプ力を鍛えるためにはうさぎ跳びだー!!」って、うさぎ跳びをひたすらやらされたとテレビでおっしゃっていた芸能人さんがいました。科学的に見ると、うさぎ跳びはジャンプ力を鍛えるために有効な手段ではなく、他の筋トレをするべきだと今の研究では言われているそうです。
つまり根性のみを鍛えていたことになりますね。昭和は根性論がメジャーだったから、「部活中に水を飲むな!」も普通でしたし、その頃の名残りなのでしょうか?
同様に、無痛分娩や帝王切開が批判の的になっていることも気になります。「帝王切開で産んだ=陣痛を経験せず楽をしている=母性が育たない=母親じゃない」みたいな批判に苦しめられている人が本当に気の毒です。
私の勝手な意見ですが、出産の日っていうのは「新しい命の誕生を喜ぶ日」だと思うんです。だから、どんな方法だっていいじゃないですか。どんな方法だって命の誕生は奇跡だし、尊いに違いありません。
また、専業主婦のママさんや保育士さんの仕事を「大したことないだろ」ってバカにする人もいますよね。(私はめっちゃ大変だと思いますが。)
あれは子どもが可愛いし、子どもと遊んでいるママさん・保育士さんが笑顔だからっていうのもあるのではないでしょうか?
楽しそうなことをしている・幸せそうだ=苦痛に耐えていない=価値がない→辛い思いをして嫌な仕事に耐えている自分のほうが立派だ…みたいな気持ちなのかもしれません。
こんな根性論は早く廃れてほしいですね。
ちょっと脱線しましたけど、私は仕事が好きです。
自分が仕事を楽しいと思いながら追求して、お客様が「こんなに良いサービスをありがとう!」って喜んでくれて、経済が回って…Win-Win-Winの「三方良し」じゃないですか。
なんでわざわざ楽しいと思うことを避けて、辛くてつまらないことを選択して、嫌々作業した質の低いサービスをお客様に提供しなければならないのか、意味がわかりません。
(辛いことを乗り越えるのも人生で良い経験かもしれませんが「辛さだけしか価値になり得ない」っていうのは違うと思います。)
そんな風に思っていた私は、出版という仕事に愛を持って向き合っている吉田さんに、簡単に魅了されてしまったのでした。
第1章「いい本」とは何か?
吉田さんは100人に「いい本」の定義を聞いてみたが、誰も「いい本」を定義づけられなかったとのことです。
そして、「いい本」には「売れる」という要素が必要だけれども、売れない本=「よくない本」は違うとのこと。
売れない本には2種類あります。
ひとつは、「売ろうと思って出版したけど、売れなかった本」
もうひとつは、「読者は少ないけれど、出版する意義がある本」です。
(中略)後者は、確信犯なのです。たとえば、難病で苦しんでいるのに認定患者の数が非常に少ない場合、その病気の研究をした解説書を出版してもほとんど売れません。しかし、「情報を必要としている人に届ける」という出版の使命から考えると、売れない本でも出す意義があるのです。
「本を出したい人の教科書」p.35-36
セラピストの仕事に悩む|お客様vsお店の経営の葛藤
私は仕事が好きだからこそ、悩むことがありました。私の職業はセラピストですが、腕が上がれば上がるほど、お客様の体は楽になるので来店頻度が落ちたり、サロンを卒業…つまりその後来なくなることもあります。
私はそれでいいと思ってます。だって体が辛くなくなるなんて、最高じゃないですか。
サロンに来ていた時間とお金を、快適で楽しい日常生活を過ごすためにぜひ使ってほしいですね。感染症のことがなければ、ぜひ家族旅行とかに使ってくださいって思います。
だけど経営のことを考えれば、テキトーに手を抜いたサービスを提供して、1回の来店で済むものを3回になるように調整したり、「これだけだとほぐしきれないので~」とオプションの追加を提案したほうがいいんですよね。
なんか、バカみたいじゃないですか。
って言うと口が悪すぎますかね、すみません。
「なんでこの会社の利潤のために、目の前のお客様に正直に向き合えないんだろう?」って不思議で不思議でしょうがないです。(株式会社が利潤を追求するのは当然のことと頭ではわかっているんですけれども。)
副業でも葛藤|そんなに偉い?
私がブログとか電子書籍を始めたのは、「これを読んで気持ちが楽になった」とか「役に立った」と思ってもらえるような情報を提供したかったからです。その結果として、巡り巡ってお金が自分にも入ってきたら、人助けにもなって副業にもなって一石二鳥だろうと思いました。
在宅でできる副業として物販(せどり)も調べていたのですが、例えば化粧品で言うと、私だったら「体にいいもの」を売りたいと思います。だけど物販は「売りたいもの」を売るのではなく、「売れているもの」をリサーチして安く仕入れて売るっていうやり方なんですね。
それが例えば添加物まみれで、「これは大事な人(リアルで会う人も、画面の向こう側のユーザーさんも)にはオススメできないな、長期的に見てお肌に良くないな、健康を害するかもな」ってわかっている、気の進まないものでも、それが世の中の売れ筋だったら、それを仕入れて売らなきゃいけないんです。
「そんな仕事を頑張るモチベーションは、私には湧かせることはできない」と思い、仮に稼げても嬉しくないだろうから、挑戦しませんでした。
(私が参加したワークショップではこう習いましたが、ユーザーのためを思って物販を頑張っている人も世の中にはいると思うので、物販を否定するつもりはありません。)
そしてブログを始めたばかりの頃、やっぱり誰しも「ブログ 書き方」なんて検索するじゃないですか。
そうしたら「こういうターゲット層を狙えば稼げます」とか「こういう分野・商品だったら稼げます」とか、そういうのばっかりで…
「売れることだけがそんなに偉いのかよ!!」
って一時期ブログも嫌になりましたが、再び浮上しました。(^_^;)
「もういいや、私は私のやり方でやっちゃおう」と腹をくくった…というとカッコイイですが、諦めました。王道メソッドを学んでそれに従うことを。
出版の目的は何のため?|どの「しごと」をする?
吉田さんは「読者は少ないけれど、出版する意義がある本」 を「使命本」と読んでいますが、私も使命本のような活動をこれから先やっていきたいです。
「しごと」には「死事・私事・仕事・志事」と色々な当て字があるみたいです。
(参考→「経営者のミカタ・管理職のミカタ! > 死事・私事・仕事・志事・・・社員全員が「志事」をすれば、仕事が本当に楽しくなる。」)
私は利益がどうとか、人からどう思われるとか、常識とか、そんなことはどうでもよくて(笑)、「好きなことを好きなときに好きなだけやる」、それが同時に仕事になっているタイプ。
つまり「私事」なんです。自分勝手な奴なんです。
でも自分勝手にやっていることだけど、楽しいから自然と上達するんですよね。それが結局お客様の役に立っていて、喜んでもらえるわけだから、結果オーライとしています。
そんな自分勝手な私ですが、これからは「自分が生まれてから死ぬまでに果たす使命」を意識して仕事の選択などをしていきたいなぁと思うようになりました。
この本の4章でも出てくるのですが、何がモチベーションになるのかは人によって違います。
私みたいに、愛とか社会貢献とか使命と聞いてモチベーションが湧いてくるよってタイプの方は特に、簡単に「本を出したい人の教科書」に引き込まれるでしょう。(笑) 「出版に興味を持ってよかったな」って思えるはずです。
さて、これを読んでいるのは電子書籍作家さんが多いでしょうか?
あなたが出版する目的は何ですか?あなたの本がこの世に生まれ出る意義は何ですか?^-^
ここまで読んでくださり、ありがとうございます!
スポンサーリンク

